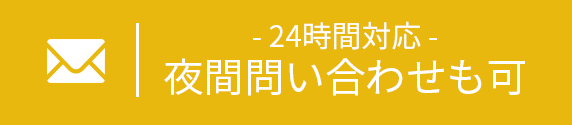コラム
交通事故の賠償金の相場はいくら?請求できる慰謝料や計算方法を解説!
2025.04.07 慰謝料交通事故にあった際、どの範囲まで損害賠償を請求できるのかわからず、保険会社から提示された金額が適正かどうか迷う方は少なくありません。本記事では交通事故の賠償金相場や慰謝料の種類、計算方法を詳しく解説します。
交通事故にあった際、損害賠償をどこまで請求できるのかわからず、保険会社の提示額が妥当なのか悩む方は多いです。
適正な賠償金を受け取らなければ、金銭的な負担が大きくなり、今後の生活にも影響を及ぼすかもしれません。
本記事では、交通事故で請求できる賠償金の種類や相場、計算方法について詳しく解説します。
一読すれば、自分のケースに合った適正な賠償額を知り、損をせずに請求できる方法がわかります。
とくに、弁護士に依頼するメリットを理解することで、より有利に交渉できる可能性が高まるでしょう。
交通事故で請求できる賠償金の範囲は?
交通事故について損害賠償を請求できる範囲には、経済的な損害と精神的な損害の2種類があります。
まずはそれぞれの損害について具体的にどのような名目で損害賠償請求が可能なのか見ていきましょう。
経済的な損害
交通事故によって発生した費用や収入の減少は、経済的な損害として加害者に請求できます。
治療にかかった費用だけでなく、仕事を休んだ際の収入減少なども含まれます。
具体的な項目は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 診察、手術、入院、投薬などにかかった費用 |
| 通院費 | 病院までの交通費(タクシー代やバス代など) |
| 付添日 | 被害者の介助や看護にかかった費用。入院・通院・自宅療養・通学時の付き添いにかかるもので、症状固定までの期間が対象 |
| 診断書の費用 | 診断書や後遺障害認定のための書類作成費用 |
| 義肢等の費用 | 事故で義足や車椅子が必要になった場合の費用 |
| 休業損害 | 仕事を休んだことによる収入の減少分 |
| 雑費等 | 入院中の日用品や食事代などの費用 |
精神的な損害(慰謝料)
交通事故によって受けた精神的苦痛に対しては、慰謝料を請求できます。
これは、被害者が感じる不安やストレス、生活の質の低下などを補償するものです。
慰謝料にはいくつかの種類があり、詳しくは後述します。
交通事故で受け取れる慰謝料は何がある?
交通事故によって請求できる慰謝料の種類は下記の3つです。
- ・入通院慰謝料
- ・後遺障害慰謝料
- ・死亡慰謝料
それぞれについて解説します。
入通院慰謝料
交通事故で負ったケガの治療のために病院へ通った場合、入通院慰謝料を請求できます。
慰謝料額は、通院や入院の日数、ケガの重さ、治療の必要性によって変わります。
通院回数が多かったり、入院期間が長かったりすると、精神的苦痛が大きいと判断されやすく、慰謝料も増額されやすいです。
仕事を休まなければならなかった場合や、普段の生活が大きく制限された場合も、精神的負担が重いと認められることがあります。
後遺障害慰謝料
交通事故のケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺症が現れると、仕事や日常生活に影響が出るため、精神的な負担も大きくなります。
慰謝料の金額は、後遺障害の等級によって決まり、等級が高いほど増額される仕組みです。
等級認定を受けるには、医師の診断書や検査結果をもとに申請を行い、適切な書類をそろえる必要があります。
死亡慰謝料
死亡事故のケースでは、遺族は死亡慰謝料を請求できます。
これは、亡くなった本人が受けた精神的苦痛と、残された遺族が被る悲しみを補償するものです。
慰謝料には、被害者本人に対する分と、遺族が受け取る分の2種類があります。
支払いを受けるのは、亡くなった人の法定相続人となる配偶者や子ども、親などです。
交通事故による賠償金の相場はどのように決定するか?
賠償金については、治療費や通院費など経済的な損害の多くは妥当と考えられる実費です。しかし、慰謝料のように実費が存在しないものは基準を用いて金額を算出します。
損害賠償額を算出する上で用いられる基準は下記の3つです。
- ・自賠責基準
- ・任意保険会社基準
- ・裁判(弁護士)基準
それぞれについて解説します。
自賠責基準
自賠責基準は、事故被害者に最低限の補償を行うための基準です。
すべての車両に加入が義務付けられており、事故が起きた際にはこの保険を利用して賠償を受けられます。
ただし、自賠責基準による賠償金額は一定の範囲に制限されており、実際の損害をすべて補えるとは限りません。
補償額は最大で120万円までです。
任意保険会社基準
任意保険会社基準は、各保険会社が独自に設定する賠償基準です。
賠償額は自賠責基準よりも高くなりがちですが、詳細な計算方法は公開されておらず、保険会社ごとに異なるため一律の基準はありません。
一般的に、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は自賠責基準を少し上回る金額が提示されます。
ただし、保険会社は支払う金額をおさえようとする傾向があり、提示された賠償額が適正かどうか慎重に判断する必要があります。
裁判(弁護士)基準
裁判(弁護士)基準は、過去の裁判例をもとに算出される賠償基準です。
他の基準に比べて高額になることが多く、慰謝料額は大きくなる傾向があります。
入通院慰謝料では、自賠責基準の約2倍以上になることもあります。
ただし、弁護士基準での賠償金を得るには、加害者側との交渉や訴訟をすすめる必要があり、専門的な知識が欠かせません。
適正な賠償を受けるためには、弁護士に相談し、示談交渉や裁判を有利にすすめることが重要です。
各賠償金の相場の算出
損害賠償の算出には3つの基準があることを解説してきましたが、これらの基準がとくに重要になるのは、経済的な損害にあたる付添費と休業損害、慰謝料全般です。
自賠責基準と裁判(弁護士)基準をもとにそれぞれについての相場を解説していきます。
相場:①付添費
入院時の付添費は、自賠責基準では1日4,200円、弁護士基準では1日6,500円です。
通院時は、自賠責基準で1日2,100円、弁護士基準で1日3,300円となります。
自宅療養時は、自賠責基準で1日2,100円です。弁護士基準では状況に応じて3,000円または6,500円以上が認められることもあります。
職業付添人の利用が必要な場合は、実費を請求可能です。
専門家による介護が求められるケースでは、弁護士基準で日額8,000円以上が認められたこともあります。
| 付添費の種類 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入院付添費 | 1日4,200円 | 1日6,500円 |
| 通院付添費 | 1日2,100円 | 1日3,300円 |
| 自宅付添費 | 1日2,100円 | 1日3,000円~6,500円以上 |
相場:②休業損害
休業損害は「休業日数×基礎収入の日額」が計算式です。
基礎収入の日額は、自賠責基準と裁判(弁護士)基準で異なります。自賠責基準は、一律で日額6,100円が適用され、裁判(弁護士)基準では、事故前の収入から計算されます。
そのため裁判(弁護士)基準は、実際の減収額に近い金額を受け取れる可能性が高いです。
| 基準 | 基礎収入(日額) | 計算方法 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 一律6,100円 | 休業日数×6,100円 |
| 裁判(弁護士)基準 | 実際の収入を基準に算出 | 休業日数×事故前の収入の日額 |
相場:③入通院慰謝料
自賠責基準では、1日4,300円を基準に支給額が決まります。
慰謝料の対象となる日数は、
- ・治療期間全体の日数
- ・実際の通院日数を基にした日数×2
のどちらか少ない方です。
この対象となる日数に4,300円を掛け合わした額が入通院慰謝料です。
裁判(弁護士)基準では、日本弁護士連合会の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている算定表が用いられます。
「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、入院・通院の期間に応じて金額が決まる仕組みです。
たとえば、骨折(重症用)を例にして以下に各基準での慰謝料相場を示します。
| 通院期間 | 実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 12日 | 10万3,200円 | 19万円 |
| 2か月 | 25日 | 21万5,000円 | 36万円 |
| 4か月 | 40日 | 34万4,000円 | 67万円 |
| 5か月 | 55日 | 47万3,000円 | 89万円 |
相場:④後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、等級が1級から14級まで細かくわけられており、重い障害ほど慰謝料も高額です。
最も重い1級では自賠責基準で1,650万円が認められる一方、軽度な14級では32万円と、大きな差があります。
弁護士基準を適用すると、自賠責基準よりも高い金額を請求可能です。
等級に対する各基準の慰謝料は下記の表のとおりです。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 裁判(弁護士)基準 |
|---|---|---|
| 1級(介護あり) | 1650万円 | 2800万円 |
| 1級 | 1150万円 | |
| 2級(介護あり) | 1203万円 | 2370万円 |
| 2級 | 998万円 | |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
相場:⑤死亡慰謝料
死亡慰謝料の金額は、自賠責基準では被害者本人に一律400万円が支払われ、遺族には請求人数に応じて550万〜750万円が認められます。
扶養家族がいた場合は、200万円が加算される仕組みです。
一方、裁判(弁護士)基準では、被害者の社会的立場や家族構成に応じて金額が決まり、一般的に2,000万円〜3,100万円の範囲となります。
| 基準 | 被害者本人の慰謝料 | 遺族の慰謝料 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 自賠責基準 | 400万円 | 550万〜750万円 | 最大1,350万円(+扶養加算200万円) |
| 裁判(弁護士)基準 | 2,000万〜3,100万円(被害者の社会的立場により変動) | 2,000万〜3,100万円 | |
弁護士に依頼するメリット
ご自身のケースに関して交通事故の損害賠償相場を知るためには、まず弁護士に相談して解決を図ってみるのがおすすめです。初回は無料としていたり、電話対応してくれたりする法律事務所もあります。
その理由は下記の3つです。
- ・裁判(弁護士)基準を用いた慰謝料請求が可能
- ・損害賠償額の増額が期待できる
- ・等級認定や過失割合についてもサポートを受けられる
それぞれについて解説します。
裁判(弁護士)基準を用いた慰謝料請求が可能
弁護士が代理人として交渉することで、裁判(弁護士)基準を適用しやすくなります。
保険会社は通常、自社の基準で慰謝料を提示しますが、裁判(弁護士)基準よりも低いことが多いです。
弁護士に依頼すれば、裁判例に基づく適正な基準で請求できるため、本来受け取れるべき金額を確保しやすくなります。
損害賠償額の増額が期待できる
上述のとおり交通事故の示談では、相手保険会社が提示する賠償額は適正でないかもしれません。
弁護士に依頼すれば、事故の程度や被害の大きさを事案ごとに詳細に分析し、適正な金額を主張できます。
加害者に重大な過失がある場合や、被害者の精神的苦痛が大きいと判断されれば、慰謝料が増額されることも多いです。
過去の裁判例をもとに、法的に根拠のある主張を行うことで、示談の段階でも適正な賠償額を得る可能性が高くなります。
等級認定や過失割合についてもサポートを受けられる
後遺障害等級の認定や過失割合の決定は、損害賠償額に大きく影響します。
しかし、適正な認定を受けるためには、専門的な知識が必要です。
必要な資料の準備や医師への説明が重要になるため、弁護士のサポートを受けることで軽減できる負担が大きいです。
また、弁護士は過失割合の見直しも対応できます。
たとえば、保険会社が7:3と判断した事故でも、証拠をもとに交渉することで8:2や9:1に修正できることもあります。
交通事故の賠償金相場を知りたい際は弁護士に相談を!
本記事では、交通事故で請求できる賠償金の種類や相場、計算方法などの情報を解説してきました。
ポイントは下記のとおりです。
- ・自賠責基準・任意保険基準・裁判(弁護士)基準の各基準によって損害賠償請求できる休業損害や慰謝料額が異なる
- ・適正な賠償金を得るには保険会社の提示額を鵜呑みにせず、裁判(弁護士)基準を確認すること
- ・弁護士に相談すると増額の可能性が高まる
自身の事故状況を整理し、どの慰謝料が請求できるのか確認し、必要に応じて弁護士に相談して適正な賠償を求めましょう。
裁判(弁護士)基準を活用すれば、より高い慰謝料を得られる可能性があるため、示談交渉前に弁護士へ相談することが大切です。